【広告】片麻痺おススメグッズ紹介
こんにちは、生活期専門の補装具製作所「装具ラボSTEPs」代表 義肢装具士の三浦です。
ここでは、装具の作製・修理に関わる補助の申請についてご説明します。
装具を作製するとき、まずは自分が作る装具が治療用装具か更生用装具かによって、利用する制度が変わってきます。
自分が利用するべき制度がかわからない!という方は、ネット調べてみるとわかりやすいフローチャートがいろいろあるので、まずはこちらをご覧ください。
治療用装具、更生用義肢・装具とは | 株式会社 佐々木義肢製作所
支給制度の選択|制度について | 支援機器イノベーション情報・支援室
はい、それではみなさんご自身が該当するであろう制度が、なんとなくわかったと思います。
ここからは架空の人物をもとに、申請についてご説明していきます。
治療用装具の医療費還付請求(払戻し請求)
初めての装具作製(治療用装具)の例
まずは、病院で治療用装具を作った場合の例をご紹介します。

脳卒中を発症して、入院中の病院で短下肢装具を作ることになりました。
先日、義肢装具士さんが来て、装具代金が約8万円かかると聞きました。
まさか全額自己負担ではないですよね…??

もちろんです!医療保険が適応になるので自己負担は1割~3割になります。
Aさんは現在、健康保険はどちらの保険に加入していますか?

えーっと、働いているので社会保険だとは思うのですが…
こちらが今使っている保険証です。

発症まで健康であった人ほど、Aさんのようにご自身の加入している健康保険について、意外と知らない場合が多いです。
そんな場合は健康保険証を確認すれば、必ずご自身の健康保険の運営元(保険者)が書いてありますよ。

Aさんの健康保険は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」で、年齢が70歳未満なので医療費は3割負担ですね。
治療用装具の場合、装具代金は一度、全額立替払いをします。
その後、ご自身で健康保険の運営元(保険者)に請求する流れになります。

なるほど、じゃあ二万五千円ぐらいの負担か、ちょっと安心しました。
装具代金の請求に必要な書類があれば教えてください。
還付請求に必要な書類

はい、必要な書類は
①装具代金の領収書(装具の種類や内訳が明記されたもの)
②医師が記入・証明した「治療用装具製作指示装着証明書」
③療養費支給申請書(必要事項をご自身で記入したもの)
の3点です。①②は装具作製、支払い後にAさんの手元に渡るはずです。③はご自身で保険者から取り寄せが必要です。
請求する装具の種類や、請求先によっては装具の写真やそのほか追加の書類が必要になる場合があります。
詳しくは、健康保険の運営元(保険者)にお問い合わせください。
装具と高額医療制度について

わかりました。
ところで、今月は医療費がかなりかさみそうなのですが、高額医療制度はつかえるのですか?

はい、装具代金も自己負担分は高額医療制度の対象となります。
そちらも、健康保険の運営元(保険者)に申請をお願いします。
その他にも、市区町村(役所・役場)で定められた補助制度(こども医療・重度障害医療など)や任意保険の補助を受けられる場合もあるので、それぞれの運営元に確認してみましょう。
更生用装具の支給申請について
退院後の装具作製(更生用装具)の例
次に、病院を退院した後に、装具を新しいものに作り替えたいと思った場合を説明します。

無事に退院して2年が経ちました。障害者手帳も取得したし、装具とは長い付き合いになりそうです。
最近足が少し細くなったようで、装具が合わなくなってきました。作り替えを考えているのですが、もう元の病院には通院していないしどうしたらいいのでしょうか?
障害者手帳を取得した後は、基本的に「障害が固定した」とみなされます。
その場合、次に作る装具は更生用装具とよばれ、厚労省が定める補装具費支給制度を利用することになります。
申請窓口はお住いの市町村役場の障害者福祉担当課(地域によって担当課の呼び名は違います)になります。

治療用装具とは申請先が変わるのですね。
前回と同じように、装具を作製した後に申請すればよいのですか?
申請の手順について

いいえ!更生用装具の場合は装具を作製する前に、市町村役場に対して補装具支給申請をする必要があります。
ここの順番は大切なので、間違えないように気を付けてください。
市町村の担当課は装具使用者からの申請を受けて、装具の作製が適切かどうか審査します。
※審査→支給決定までの流れは市町村によって大きく異なります。必ず、お住いの市町村の障害者福祉担当課にお問い合わせください。
更生用装具の支給に関して詳しい内容は、厚生労働省「補装具費支給制度の概要」と「サービス利用方法」をご覧ください。

なるほど、治療用装具の時は病院の治療方針に従って装具の作製が決まり、どちらかというと受け身で装具の作製が進みました。
更生用装具になると、より能動的に私自身が動かないといけないのですね。
更生用装具の考え方

仰る通りです。「障害者自立支援法」という名称からして自発的な行動が求められているのがわかりますね。
そのため、私たち周囲の医療・介護職がどれだけ必要を感じたとしても、ご本人にその意思がなければなんともなりません。
それが「装具難民問題」の難しい面でもありますね…。
話はそれましたが、ご負担額については以下にご説明します。
負担額は支給決定された装具の原則一割負担です。
ただし、負担上限額は37,200円と決まっています。市町村民税の非課税世帯に関しては、補装具費の利用者負担はゼロです。
また、市町村民税所得割の納税額が46万円以上(最多納税者)の場合には補装具費の支給対象外となります。
詳しい内容は厚生労働省「補装具の利用者負担」をご覧ください。
装具の修理を行う場合の申請方法について
装具の修理も補助がでるのか?
最後に、装具の修理を行う場合の費用負担ついてご説明します。

装具の修理に関しても、補助がでるのですか?

はい、装具の修理に関しても申請ができます。
治療用装具として作製した装具の修理は、療養費支給制度を利用して医療保険窓口に申請。
更生用装具として作製した装具の修理は、補装具費支給制度を利用して市町村役場に申請。
となります。申請の流れは作製の時と同様です。

そうなんですね。先日、更生用装具として新しく装具を作製しました。
古い方の治療用装具を、予備として使えるようにベルトを交換しておきたいです。
それだけのために病院を受診するのは億劫ですね…。
自費での修理も可能か?

そういうことでしたら、自費での修理も可能ですよ。
申請にかかる手間と費用負担を天秤にかけて、自費で装具の作製や修理を行う人は案外多いです。
各部の修理にかかる費用に関しては、こちらの記事をご覧ください↓

これぐらいの負担でしたら、今回は自費でお願いします。
新しい装具が出来上がって、古い装具も予備として備えられるので安心ですね。
以上が制度に関する説明でした。
ここにご説明した以外にも、労災や生活保護、交通事故など申請窓口が異なる場合があります。
基本的に、義肢装具の支給方法に関しては、申請先(保険者)が定めたルールに従うことになります。
義肢装具支給制度選択チャートをもとにご自身が利用する制度を確認し、各制度の担当窓口に問い合わせましょう。
最後に、このブログのお供として手元に置いていただきたい本を以下にご紹介します。この本を読めば補装具申請に関する基本的な考え方やわかりにくいポイントについて詳しく知ることが出来ます。ぜひご覧ください。
装具の修理・作製のご相談は装具ラボSTEPsホームページ内の問い合わせフォームよりお待ちしております。
生活期専門補装具製作所「装具ラボSTEPs」は神戸を拠点に活動していますが、今後は全国各地に拠点を作って装具に困っている人をゼロにすることを目指しています。
気になった方は、装具ラボSTEPsで検索してみてくださいね。
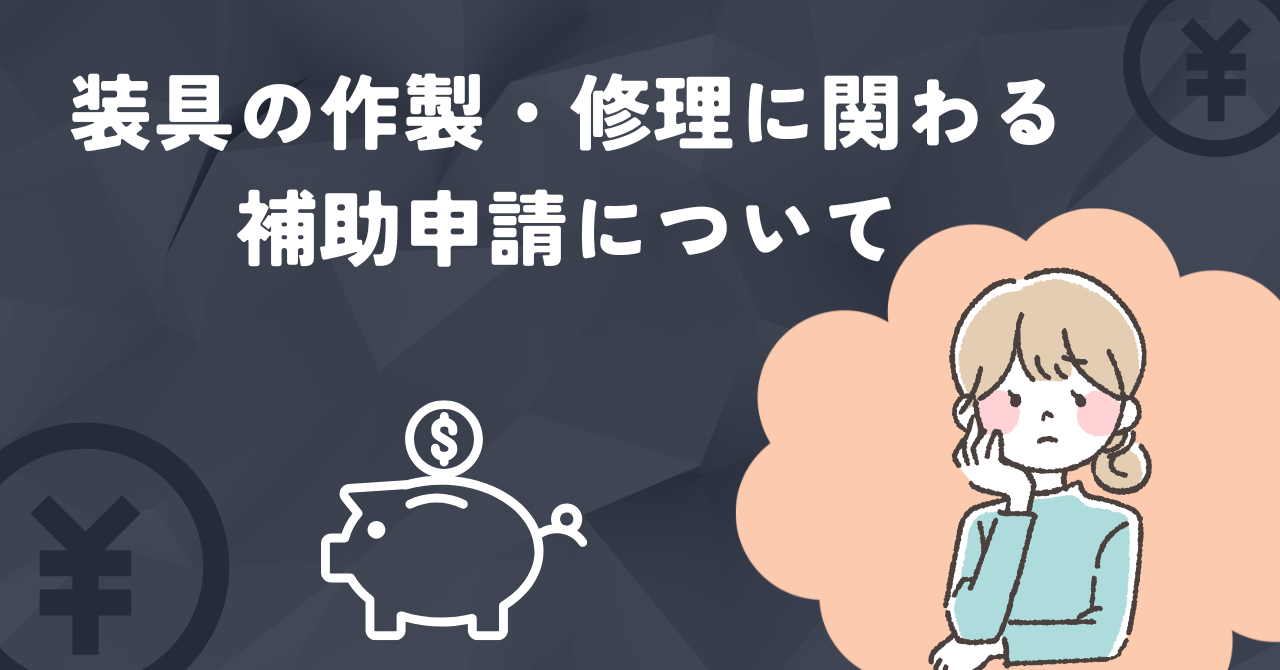

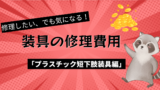
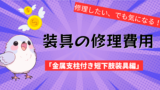


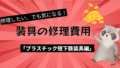

コメント