【広告】片麻痺おススメレシピ本紹介
こんにちは、生活期専門の補装具製作所「装具ラボSTEPs」代表 義肢装具士の三浦です。
ここでは、歩行リハビリ用の装具として使われることが多い、長下肢装具についてご説明します。
長下肢装具とは
長下肢装具の特徴
長下肢装具とは股関節から下の部分を支えるための装具です。
直接的に影響するのは膝の動きと足首の動きですが、膝と足首の動きを装具で制御することで、股関節の動きを助ける役目を果たします。
短下肢装具は「足首を制御することで、膝の動きを助けるため」
長下肢装具は「膝と足首の動きを制御することで、股関節の動きを助けるため」
つまり、体重を支えている下肢の装具に関しては、土台となる下をしっかりと安定させることで、上を安定させる目的があります。
サムネイル画像にある通り、まさにジェンガのような感じです。
長下肢装具の見た目と各部名称

上の図では、全て金属パーツ以外は革やフェルトで作られていますが、金属パーツ以外の部分がプラスチックで作られたものもあります。
それでは、ここからは架空の装具ユーザーさんを例に出して、説明していきます。
長下肢装具の適応症例
脳卒中後遺症Aさんの場合

Aさん
はい、そういえば私も入院当初、そのイラストのような装具を使って、リハビリをしていました。
理学療法士さんが膝のロックをガチャっとかけると、まさに足全体が一本の棒のようになって、ロボットにでもなったような気分でした。
膝継手にもいろいろ種類はあるのですが、Aさんが使っていたのはおそらく一番使用頻度の多い「リングロック膝継手」ですね。
膝継手の種類は下の図に示します。


Aさん
しばらくして、だんだんと膝に力が入るようになってきたので、膝から上の部分を取り外してもらいました。
解放された気分になりましたが、やはりそれで歩くのは少し怖かったですね。
長下肢装具の膝から上を取り外して、短下肢装具に変えることを「カットダウン」といいます。
カットダウンとは
カットダウンというと、まるで切り取ってしまうようですが、実際は上下をつなげているネジをはずして分離させるだけなので、必要に応じてまた元の長下肢装具に戻すことが出来ます。

Aさん
そうそう、私があまりにも怖がるので、理学療法士さんがもう一度長下肢装具に戻してくれたこともありました💦
そうこうしているうちに、短下肢装具でもなんとか歩けるようになりました。
そうですね、みなさん一進一退しながらリハビリを進めていって、最終的に短下肢装具の状態で退院される方が多いです。
短下肢装具についてはこちら↓
脊髄損傷Mさんの場合

Mさん
私は若いころに事故で脊髄損傷になり、両足にカーボン製の長下肢装具を使っています。
長距離移動の時はさすがに車椅子を使いますが、近場や屋内は長下肢装具とロフストランドクラッチで移動しています。
日常の中で長下肢装具を使う場合、Aさんが使っているようなリハビリ用の長下肢装具とは少し意味合いが違ってきます。
例えば、立った時に自動的に膝にロックがかかる「スイスロック」という膝継手を使ったり、トイレなどで脱ぎ履きに困らないように少し太ももの支えが短めの「セミ長下肢装具」にすることもあります。
Mさんのように活動量が多い場合は、強度が高く軽量なカーボン素材とすることもあります。
カーボン製装具の解説はこちら↓
また、移動手段としては車椅子であっても、下肢筋力の維持や全身機能の維持を目的として、リハビリシーンで長下肢装具を使用している方もいます。
長下肢装具を暮らしの中で使う方は多いわけではありませんが、使う人にとっては日常生活を左右するとても重要な装具になります。
材料やパーツの選択によってはかなり高額にもなるので、信頼できる義肢装具士と慎重に検討を重ねながら作っていきたいですね。
以上が長下肢装具の説明です。
最後に、このブログのお供として手元に置いていただきたい本を以下にご紹介します。もちろん、本がなくても、このブログを楽しんでもらうことはできます。ただし、装具の情報は日々更新され、考え方も人によって大きく異なります。できるだけ多くの情報に触れることができるよう、いくつかおすすめの書籍を挙げておきます。参考にしてください。
「脳卒中の装具のミカタ」は脳卒中の装具に関して、比較的新しい情報が得られる本(2021年出版)。Q&A方式で脳卒中の装具に関するみなさんのよくある疑問をひとつひとつ丁寧に解説しているのでおススメです。最終章は生活期に関しても、言及されており他の本では得られない情報が得られます。
「義肢装具のチェックポイント」は義肢装具全般に関して広く網羅されている本。義足・義手・装具はもちろん車いすや杖についても書かれています。かなり専門的な情報まで細かく記載されているが、全て読むというより辞書的にわからないことを調べる目的で使ってもらいたい一冊です。
「脳卒中の下肢装具」は写真やイラスト多めで、下肢装具の種類がたくさん紹介されている本です。歩行の問題点に対する基本的な対処法がリスト化されていたり、短下肢装具が種類別にリスト化されていたりと、何度も見返して楽しめる一冊です。
装具の修理・作製のご相談は装具ラボSTEPsホームページ内の問い合わせフォームよりお待ちしております。
生活期専門補装具製作所「装具ラボSTEPs」は神戸を拠点に活動していますが、今後は全国各地に拠点を作って装具に困っている人をゼロにすることを目指しています。
気になった方は、装具ラボSTEPsで検索してみてくださいね。


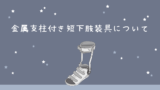







コメント